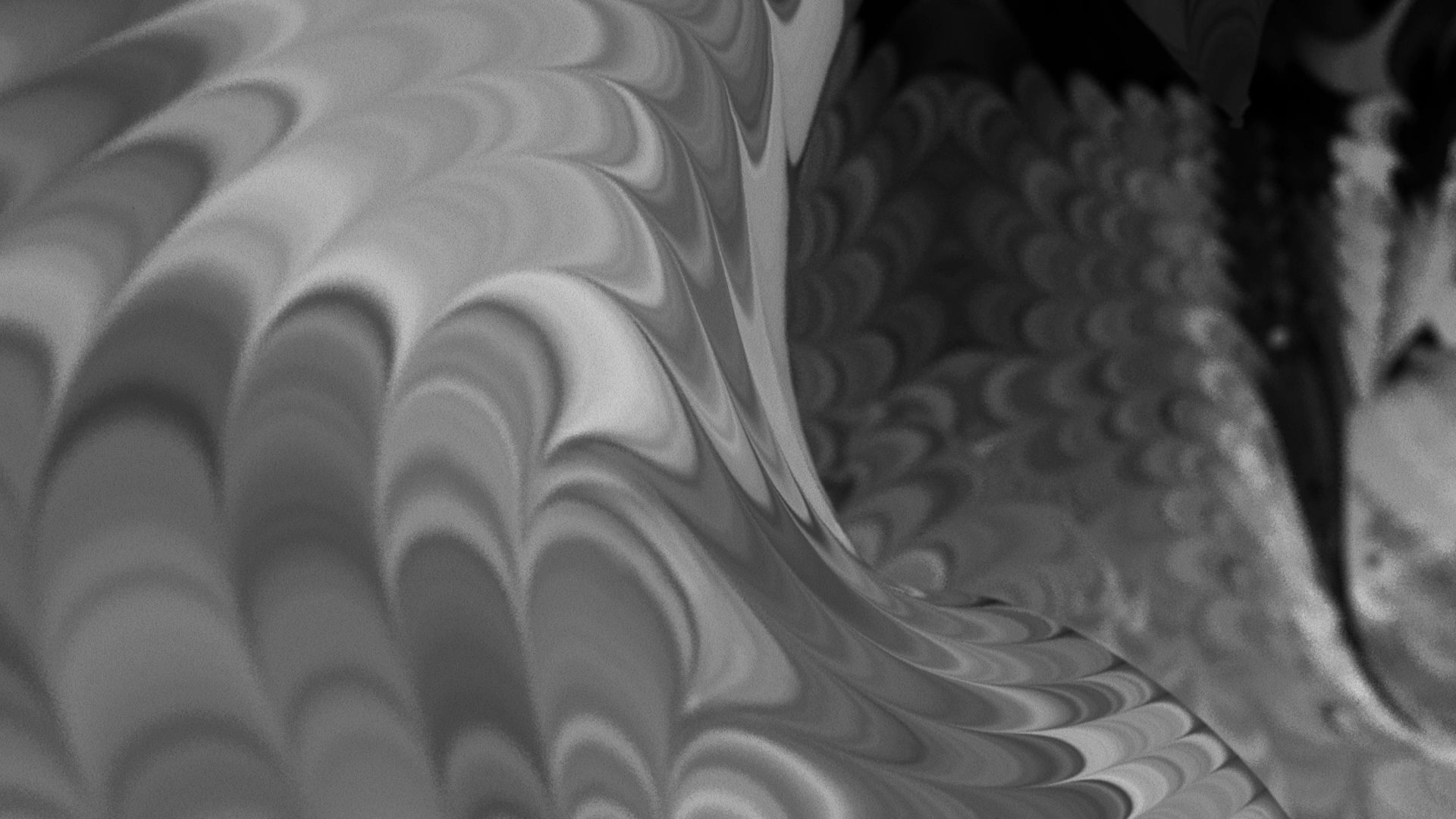
クセとトーン
ここ最近、ユーフラテス関係の方とオンライン長電話する機会が立てつづけにあった。具体的には山本 ロバート 晃士さんと石川 将也さん。ひさびさに人と制作の話をしたので、いってることが支離滅裂だし滑舌も最悪で、なかなかにひどかった。コロナ禍前に地元に移住して以降、身近に会える友人との話題が主に結婚や出産とボードゲームの話だったので、そのあたりの言語野が退化したような気さえする。
で、別にそれが本題じゃなくて、僕の中での長年のプチ疑問をぶつけてみたかったんだけど日和ってあんまちゃんと聞けなかったって話。 雑にいってしまうと「佐藤雅彦研出身者界隈の方々のつくるトーンは、どうしていつもピタゴラッとしているのか」という質問だ。それを「ピタゴラ感」そのもののオリジネーター達に聞くのも変だし意味がわからない。そもそも僕のこれまでキャリア自体が、藝大の佐藤研に行けなかった反動形成だったりするので、敬愛と僻みとが混じりあったドロドロとした感情が、その手の失礼をさせてしまうのかもしれない。
そういえば 3 年前、Flyの MV のインタビューを伊藤 ガビンさんから受けていた時にもそういう話題になったっけ。ガビンさんからの伝聞によると、その疑問に対してとある“研”出身者の方は「そもそも取り組んでいる問題が佐藤先生と同じなので」と語っていたらしい。ああいった〈気づき〉や〈認知〉の面白さをより明瞭に浮き上がらせるにはピタゴラ的トーンは一つの最適解で、そこに収斂進化するのは否定的に捉えることでもない、と。一理あると思った。
そもそもピタゴラ感を見慣れたものだと感じてしまうのは、多分僕が物心あるころから佐藤雅彦さん的ユルさに慣れ親しんでいたからなんだろうな。初めて買った NEC 機にはバザールでござーるの壁紙がプリインストールされていたし、ピタゴラスイッチの放映開始は小 5 のときだ。だからそれ以前の教育番組に対して、「ピタゴラ」がどのくらいフックのある表現だったか、そして攻めた佇まいだったかを相対視できてない。ただ、ご本人を存じあげない一視聴者としては、佐藤雅彦さんが作られるものは決してニュートラルでプレーンなものではなかったと思う。さも教育的な体を装いつつも、むしろ不条理とユルさとの不気味な共存関係が、つくり手の意図しないところで漏れ出しているような、そんな印象があった。あの作為の読めなさ——どこに焦点が定まってるのか見てとれない雰囲気が、小学生の僕や同級生に妙な引っ掛かりを残していた。あのトーンが、『IQ』しかり、かなり意図的にデザインされていたのを知るのは僕が成人してからだ。
この十数年を経て、「ピタゴラっぽさ」は至るところに浸透してきたと思う。世の中一般の思うピタゴラ感は僕らの想像以上に粒度が粗いので、高校の友達がいうには『テクネ』や『デザインあ』もピタゴラっぽくみえるらしい。(前者に至っては川村真司さんだし…)つまり、あの種のトーンは、良し悪しの話とは全く別に、あまりにフォロワーが多くなりすぎて、フックとしては既に機能していないってことなんだと思う。広告はアートだなんて言われていた感性消費の時代へのある種の反抗として ♪ スコーンスコーン...と連呼したあの精神性、エッジーさを今現在に体現するなら、もっと違ったクセのスゴさがそろそろ発明されても良いような気がする。柴田大平さんはその境界を押し広げようとされているような印象を勝手に持っている。
なんか、そういう意識をふんわり抱きつつ 4 年前に作ったのがこの MV だった。
モノクロームなスナップ写真の、奥行きに対する無意識の予想が裏切られていく浮遊感を表現しようとしたのだけど、その認知的面白さを全面に押し出すならば、まだまだ要素を削ぎ落とせたかもしれない。音楽もエクスペリメンタル系ではなくサラっとした感じに出来ただろうし、ナレーションだって入れても良かった。途中のマーブル模様に映像が溶け出す下りは単にグラフィカルなだけで、映像の技法としての主題を伝えるには蛇足だ。だけど、もしシュッとした表現に削いだところで、観る人は作品から透けて見える作り手のアティテュードの均質性にはとても敏感なもので、サムネイルをひと目観た瞬間に、ああ、そういう感じね、とスルーされてしまうような気がする。たとえ「そういう感じ」が明確に言語化できなくとも。少なくとも自分の中にはそういう強迫観念があって、それが作品に対して天の邪鬼にクセのスゴさを付加させんとしてる。もちろん、目の惹きやすさを安直に突き詰めた先にあるのは国内 YouTuber のバカデカいテロップや Twitter の創作実話のようなアテンション・エコノミー地獄だったりするのだけど、あれはあれでまた別種の「そういう感じ」に収まってるとも言えるし。
分かる。反感とまではいかなくとも、なんというか教科書を見てるような気持ちになるときはある。だから、自分が作る側のときも、手法だけをシャープに伝えることへの抵抗感があるし、むしろ、手法とモチーフ、どう澄ました態度をしてみせても混じらざるを得ない個人的嗜好との総体が一つのおぼろげな印象として観た人の記憶に残ってくれれば良いなぁと思う。いや、ちょっとカッコつけたかも。ただ、歴史的にトンチ派っぽく受け止められている作品のエッセンスは、トーンやクセとひとまとまりになってることのが実際多いように感じる。例えば Virtual Insanity のビデオは、床が動く(実際はセットの方をみんなで手押ししてる)というギミックとジェイ・ケイのダンス、クソでかいゴキブリと血が渾然となって一つの世界観を提示している。川村さんが意味深にツイートしたこの有名なビデオも、スケートフィルムというちゃんと分かってる人にしか撮れないフォーマットを選んだことや、西日で白飛びした画の生っぽさが、結果としてとても個人的な感じ(語彙力)を醸し出している。
https://x.com/masakawa/status/1236231720875069440?s=20
言っておくと、技法は似ていてもトーンが違うんで、全く別物だと思っとります。個人的には AC 部フォロワーのような、トーンを低い解像度で真似した作品の方がモヤりがちです
だから、面白さの核というのは分離可能なものでも、個別に検証可能なものでもなくて、作り手のクセのスゴさや好みの押し売りと不可分なものなんじゃないかなと思ってる。この辺は自分がラピッド・プロトタイピングや「A4 一枚で伝わるシンプルなアイディア」をあまり信用してないところにも通じている。面白さの原器それ単体で伝わる良さはもちろん好き。だけど、作ってる側にははっきり見えていてもエレベーター・ピッチなんぞではとても伝えきれない込み入った情感が、手法・モチーフ・エディット全部がカチッと組み合わさることではじめて創発的に完成されるような良さも、自分には同じくらいに魅力的だったりする。ただ、もし面白さの原器をプレーンに提示しようとするがあまり、なんかそういうクセのある感じに何か拒否感を覚える方がいるのだとすれば、僕の個人的興味として、そういう真摯に表現と向き合ってる方だからこそ、クセのスゴい一面を観たいなと思わずには居られない。もちろん、そういう作家主義的なものの方が世の中に圧倒的に多いなかで、トーンというパラメーターはひとまず広義の「ピタゴラ感」に固定した上でより本質的な部分に集中するスタンスを意識的にとられているはずなので、そんなことを言うのは野暮なのだろうと反省しつつ。

ちょうどさっき、授業のお礼にと、山本晃士さん個人が主宰されているサークル〈平均律〉の同人誌が届いてとても嬉しい。山本さんは物腰の柔らかさや文章の丁寧さも含めて、つい卑屈になりがちな自分としてはかくありたい方で...。と、色々リスペクトしてる所を書き連ねたいのですが、ヨイショ感がキモいので程々にしときます。ともかく山本さんのグラフィックが好きなのは、真っ当に取り扱えば学術的で凛としたトーンに収まりやすい主題のなかで、物怖じ無くクセのスゴさが発揮されているように思えるところで。パラメトリックなグラフィック表現や識字能力というテーマにおいて、女の子のかわいさは決して本質的ではない。だけど、そういう生真面目なアレコレとか色々すっ飛ばして、良い意味で軽薄であれる感じが、傍からはとても軽やかに映るというか。僕みたいな映像作家、ニューメディアアート、観察・気づき界どっちサイドからも中途半端で頭でっかちだと思われている立場として、表現のエッセンスについて掘り続ける傍ら、そういうクセのスゴい活動をされている業界の年長者の存在に妙にホッとする。